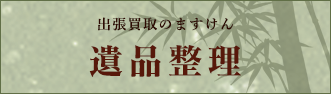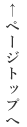コラム
- トップ
- 「呉須と金彩の新境地を切り開いた 近藤悠三」
-
コラム
「呉須と金彩の新境地を切り開いた 近藤悠三」2016/12/12

骨太の幹に大輪の花をあしらった梅の図。大胆な構図でおおらかに筆を走らせるキャンバスは、平面のそれではなく、どっしりとした陶胎そのものに描いている・・・。
明治35年生まれの近藤悠三がこの絵画的表現技法を確立したのは戦後の事でした。「野山の果実や野菜の形が自然ながら有している生命感、あのみずみずしさ、力強さ、やさしさ、そしてきびしさを、陶器もまた求めてくる」と語ったように、自身が描く柘榴や梅、山水などをモチーフとした雄渾な絵画的筆致に、時に釉裏紅彩を併用する場合も含めて、呉須の濃淡の階調による独自の境地を示しました。
この染付に金彩を組み合わせるという技法は、それまで誰も試みる事のなかった技法でありました。
その境地まで辿り着くのには近藤自身の並々ならぬ気概と努力が存在したのでした。
近藤悠三の生い立ち
近藤悠三は1902年(明治35年)、京都市に近藤正平・千鶴の三男として生まれました。12歳で京都市立陶磁器試験場付属轆轤科に入所し、大正6年に卒業、そ の後同試験場助手となりました。この時期技手を務めていた河井寛次郎、濱田庄司を知り、濱田に窯業化学等について学びました。大正10年に富本憲吉が留学先のイギリスから帰国し、大和安堵村に築窯したのを機に試験場を辞し富本の助手となりますが、2年半で京都へ戻りました。京都へ戻った理由は、轆轤の技術を会得した近藤に対し、富本が「陶器以外の勉強」を勧めたからと言われています。京都に戻ってからは富本に言われた通り、デッサンや洋画を学んだり漢詩を読んだりして陶芸以外の技術や教養を深めるとともに、自宅で作陶を始めました。
の後同試験場助手となりました。この時期技手を務めていた河井寛次郎、濱田庄司を知り、濱田に窯業化学等について学びました。大正10年に富本憲吉が留学先のイギリスから帰国し、大和安堵村に築窯したのを機に試験場を辞し富本の助手となりますが、2年半で京都へ戻りました。京都へ戻った理由は、轆轤の技術を会得した近藤に対し、富本が「陶器以外の勉強」を勧めたからと言われています。京都に戻ってからは富本に言われた通り、デッサンや洋画を学んだり漢詩を読んだりして陶芸以外の技術や教養を深めるとともに、自宅で作陶を始めました。
昭和初期より帝展・文展などに、薊・葡萄・柘榴などの模様を主題に、染付や他の多様な技法による作品を発表しましたが、戦後は呉須による染付に専念し、この伝統的技法の研究を深めながら、民芸調の素朴な力強さを加え、ロクロ成形とともに豪快雄暉で伸びやかな独自の染付けの世界を拓いていきました。
勤王の志士の血を受け継いだ陶芸家
 近藤悠三の祖父近藤正慎は平安京遷都以前からの歴史をもつ清水寺の寺侍でありました。幕末に寺の僧・月照と西郷隆盛を薩摩へ逃すために一役買い、新選組に捕えられ、京都・六角の獄中で舌をかみ切って自害するほどの勤王の志士でした。そんな正慎の孫である近藤悠三自身も一度決めた事は決して曲げず、信念を貫き通すタイプでした。例えば作陶は生活の為ではなく、貧乏をしていてもあくまで己の美を追求する為に轆轤をまわし続けました。又、叙勲や重要無形文化財に認定されたときも、「酒飲んで仕事している方がええ」と言って一度も表彰される為に東京へは行くことはありませんでした。その当時、陶芸家というのは代々続いているところしか認められないようなところがあり、近藤自身は「陶芸家の息子でなない」というコンプレックスがあった為、「その陶芸家の息子よりもいい作品を作る」という事に情熱を注いで作陶に励みました。その結果、誰もやった事のない「呉須×金彩」という境地に辿り着き、亡くなる前も「死んでも陶芸家になって戻ってくる」というほど陶芸家としての並々ならぬ気概を保ち続けたのでした。
近藤悠三の祖父近藤正慎は平安京遷都以前からの歴史をもつ清水寺の寺侍でありました。幕末に寺の僧・月照と西郷隆盛を薩摩へ逃すために一役買い、新選組に捕えられ、京都・六角の獄中で舌をかみ切って自害するほどの勤王の志士でした。そんな正慎の孫である近藤悠三自身も一度決めた事は決して曲げず、信念を貫き通すタイプでした。例えば作陶は生活の為ではなく、貧乏をしていてもあくまで己の美を追求する為に轆轤をまわし続けました。又、叙勲や重要無形文化財に認定されたときも、「酒飲んで仕事している方がええ」と言って一度も表彰される為に東京へは行くことはありませんでした。その当時、陶芸家というのは代々続いているところしか認められないようなところがあり、近藤自身は「陶芸家の息子でなない」というコンプレックスがあった為、「その陶芸家の息子よりもいい作品を作る」という事に情熱を注いで作陶に励みました。その結果、誰もやった事のない「呉須×金彩」という境地に辿り着き、亡くなる前も「死んでも陶芸家になって戻ってくる」というほど陶芸家としての並々ならぬ気概を保ち続けたのでした。
|
|
古美術ますけんが選ばれる理由
|
|
|
|
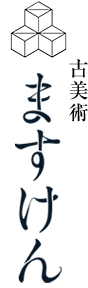
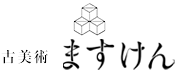
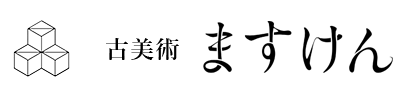
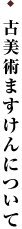
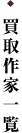
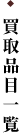
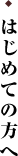
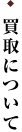
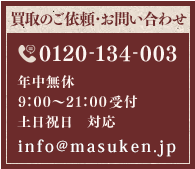
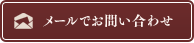
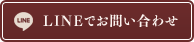






 0120-134-003
0120-134-003 info@masuken.jp
info@masuken.jp ID:@masuken
ID:@masuken
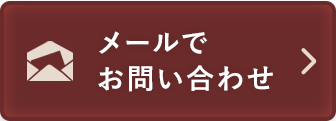
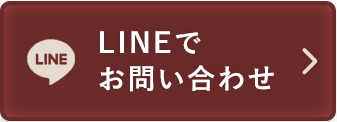
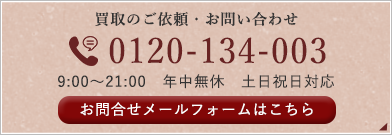
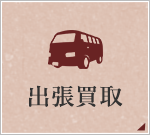
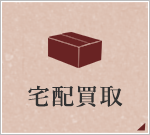

 出張費無料
出張費無料 実績多数
実績多数 安心・信頼
安心・信頼 迅速・丁寧
迅速・丁寧