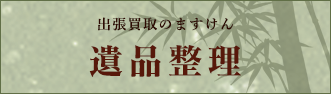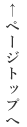コラム
- トップ
- 「形の美しさをとことん追求した井上萬二」
-
コラム
「形の美しさをとことん追求した井上萬二」2016/12/26

白磁とは、陶石や磁土を主原料として形成し、その上に長石や石灰に木灰を調合した透明釉を掛けて焼成する陶芸技法です。元々は中国で生まれた技法ですが、日本では17世紀初頭に李朝の陶工によって初めて焼造されました。加飾に頼らず、かたちだけで見せる極めて難しい技法ではありますが、その究極の白磁美に到達したのが、1995年に重要無形文化財保持者に認定された井上萬二です。
有田焼の窯元で生まれ、色絵磁器で有名な柿右衛門窯で13年修行した井上氏が、白磁の世界にのめり込む要因となったのは、有田を代表する轆轤師、初代奥川忠右衛門との出会いがあったからでした。
白磁への目覚め
井上萬二は1929年、有田町の窯元に生まれました。祖父・惣吉は大正時代に有田の南河 原に窯を開き、父・輝二も製陶を営みましたが、戦争の影響で井上が10歳の時に廃業してしまいました。
原に窯を開き、父・輝二も製陶を営みましたが、戦争の影響で井上が10歳の時に廃業してしまいました。
15歳の時に海軍飛行予科練習生として入隊し、17歳で復員。復員後は「井上製陶所を復興したい」という父の願いに応えるべく、家の隣にある柿右衛門窯で修業を始めました。
柿右衛門窯では朝7時から17時までの厳しい修行を続けて6年程経った頃。壁にぶつかり焼物を止めようかと思い悩んでいる時に奥川忠右衛門氏に出会いました。当時奥川忠右衛門はフリーの轆轤細工人であり、白磁作家の草分け的存在でもありました。その奥川は柿右衛門窯に随時請われて出張制作していたのです。そんな奥川の卓越した技術を目の当たりにし、弟子入りを決意した井上は、平日は柿右衛門窯、日曜日には奥川のところで修業するという生活が始まりました。
井上萬二窯、再興
 柿右衛門窯で13年間勤めた後、今度は窯業全体について学ぼうと佐賀県窯業試験場の技官になりました。試作品の製作や技術者養成制度において轆轤指導を行い、多くの後継者を育てました。1969年には、米国ペンシルベニア州立大学から有田焼の講師として招かれ約5カ月間、英語で作陶指導しました。その後もカリフォルニア州立大学やニューメキシコ州立大学などから要請があり、これまで計20回ほど渡米して指導しています。
柿右衛門窯で13年間勤めた後、今度は窯業全体について学ぼうと佐賀県窯業試験場の技官になりました。試作品の製作や技術者養成制度において轆轤指導を行い、多くの後継者を育てました。1969年には、米国ペンシルベニア州立大学から有田焼の講師として招かれ約5カ月間、英語で作陶指導しました。その後もカリフォルニア州立大学やニューメキシコ州立大学などから要請があり、これまで計20回ほど渡米して指導しています。
そして閉鎖されていた井上製陶所を井上萬二窯として再興し、本格的に作家活動を始めたのは42歳の時でした。
「偶然はあってはならない。どんなに難しい形でも同じものを再現できなければならない」
というストイックな精神のもと、再興依頼一貫して白磁にこだわり、轆轤技術を駆使した造形による美を追求し続けています。
|
|
古美術ますけんが選ばれる理由
|
|
|
|
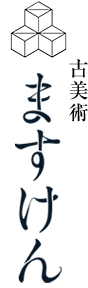
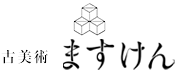
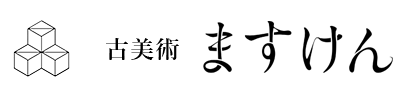
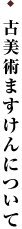
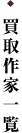
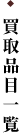
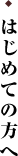
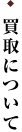
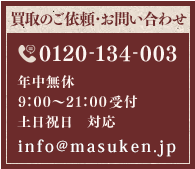
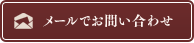
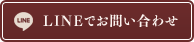






 0120-134-003
0120-134-003 info@masuken.jp
info@masuken.jp ID:@masuken
ID:@masuken
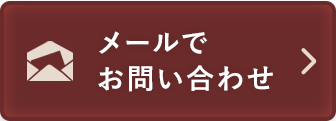
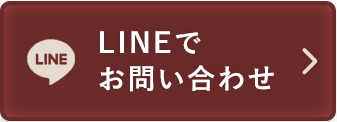
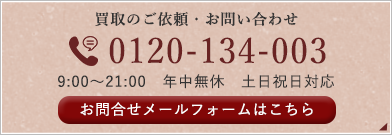
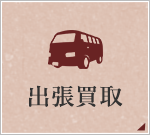
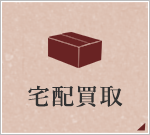

 出張費無料
出張費無料 実績多数
実績多数 安心・信頼
安心・信頼 迅速・丁寧
迅速・丁寧