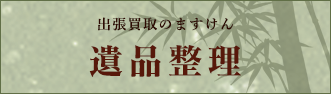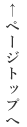コラム
- トップ
- 「桃山陶から現代備前を確立 金重陶陽」
-
コラム
「桃山陶から現代備前を確立 金重陶陽」2017/05/15

金重陶陽は明治29年に備前六姓と呼ばれる歴史ある陶家の一つである金重家の長男として生まれ、備前焼として初めて人間国宝に指定された陶芸家です。代表的な作品には桃山陶を彷彿とさせる茶陶が中心ですが、細工物の名工であった父・楳陽のもとで少年時代から陶技を学び、おもに江戸から明治時代に発達した人物・鳥獣等の細工物を得意としていました。細工物から茶陶への転向は、陶陽が30代後半にして偶然にも轆轤を挽く機会を得てからの事でした。
備前焼 細工物の名手
備前焼は桃山時代の茶陶や荒川豊蔵や川喜田半泥子らに よる「昭和の桃山復興」に見られる、釉薬を用いずに褐色の素地を長時間焼き締めたものが一般的によく知られています。しかし江戸時代の備前は、有田焼や京焼といった施釉陶磁器の人気に対抗すべく、彩色備前や白備前、青備前などの技法による手の込んだ細工物に力が注がれました。岡山藩の庇護のもと、布袋や獅子などをモチーフにし、繊細で技巧的な作調のいわゆる伊部手が盛んに焼かれた時代でした。しかし明治維新により藩の庇護がなくなると、備前の焼き物は土管や煉瓦の生産を主とする工業化が進みました。そうした情勢の中でも陶陽は個人経営の窯元で、職人に生活雑器を作らせながらも自らは辛抱強く細工物の制作に従事し、精緻で躍動感ある作品は評判になり、三村陶景・西村春湖とともに備前の3名工として知られるようにまでなりました。
よる「昭和の桃山復興」に見られる、釉薬を用いずに褐色の素地を長時間焼き締めたものが一般的によく知られています。しかし江戸時代の備前は、有田焼や京焼といった施釉陶磁器の人気に対抗すべく、彩色備前や白備前、青備前などの技法による手の込んだ細工物に力が注がれました。岡山藩の庇護のもと、布袋や獅子などをモチーフにし、繊細で技巧的な作調のいわゆる伊部手が盛んに焼かれた時代でした。しかし明治維新により藩の庇護がなくなると、備前の焼き物は土管や煉瓦の生産を主とする工業化が進みました。そうした情勢の中でも陶陽は個人経営の窯元で、職人に生活雑器を作らせながらも自らは辛抱強く細工物の制作に従事し、精緻で躍動感ある作品は評判になり、三村陶景・西村春湖とともに備前の3名工として知られるようにまでなりました。
細工ものから轆轤成形への転向
 昭和初期は陶陽が細工物から轆轤に転向していく過渡期でした。陶陽は窯主である自分が細工物をして、職人に生活雑貨を作らせていましたが、ある時初めて轆轤を挽く機会を得ました。記念すべき初めての轆轤作品は3尺5寸程の擂鉢で、思いのほかの良品に気を良くした陶陽は轆轤による制作に熱中するようになりました。
昭和初期は陶陽が細工物から轆轤に転向していく過渡期でした。陶陽は窯主である自分が細工物をして、職人に生活雑貨を作らせていましたが、ある時初めて轆轤を挽く機会を得ました。記念すべき初めての轆轤作品は3尺5寸程の擂鉢で、思いのほかの良品に気を良くした陶陽は轆轤による制作に熱中するようになりました。
折しも昭和初期の日本は荒川豊蔵をはじめとした古窯跡の発掘ブームのさなかにあり、陶陽も豊蔵や川喜田半泥子、十代三輪休雪と「かねひら会」を結成。彼らと交流を深めつつ、桃山古備前の研究を重ね、胎土の調整や窯の構造の改革などを進め桃山備前の復興に全力を注ぎました。
戦後はイサムノグチや北大路魯山人ら個性的な作家たちとの交流により、それまでの備前焼にはなかった造形性の高い様々な表現に挑戦し、作域を広げました。
1956年、陶陽は備前焼の技法で初めて重要無形文化財に認定されました。明治初期に衰退してしまった備前焼でしたが、陶陽に続いて藤原啓や山本陶秀、藤原雄、伊勢崎淳を含め、備前焼では5人もの人間国宝が誕生しました。これも陶陽が現代備前の先駆けとなって桃山備前の研究をし、独自の茶陶表現を開花させた結果です。
|
|
古美術ますけんが選ばれる理由
|
|
|
|
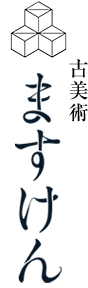
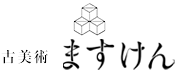
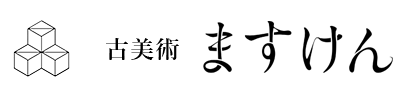
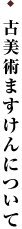
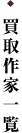
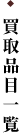
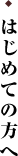
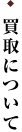
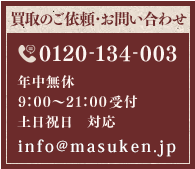
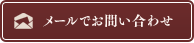
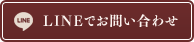






 0120-134-003
0120-134-003 info@masuken.jp
info@masuken.jp ID:@masuken
ID:@masuken
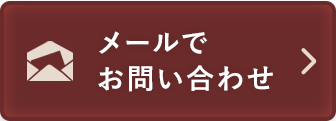
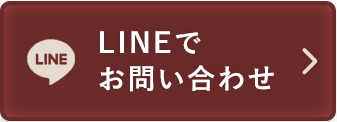
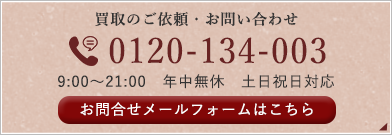
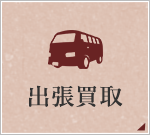
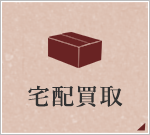

 出張費無料
出張費無料 実績多数
実績多数 安心・信頼
安心・信頼 迅速・丁寧
迅速・丁寧