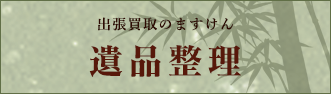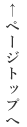コラム
- トップ
- 「青磁と色絵の融合でロマン溢れる作品 三浦小平二」
-
コラム
「青磁と色絵の融合でロマン溢れる作品 三浦小平二」2017/06/19
 青磁は本来中国で皇帝たちのために作られ、皇帝たちに愛されてきた特別な器でした。中国で最も優れた青磁が焼かれたのは宋時代で、それらの青磁の碗や壺、鉢等は鎌倉時代の日本にも伝わり、以来将軍や大名などが競って求めたといわれています。日本で青磁が焼かれるようになったのは江戸時代前期の有田地方で、江戸後期には京焼や瑞芝焼等にも広まりました。
青磁は本来中国で皇帝たちのために作られ、皇帝たちに愛されてきた特別な器でした。中国で最も優れた青磁が焼かれたのは宋時代で、それらの青磁の碗や壺、鉢等は鎌倉時代の日本にも伝わり、以来将軍や大名などが競って求めたといわれています。日本で青磁が焼かれるようになったのは江戸時代前期の有田地方で、江戸後期には京焼や瑞芝焼等にも広まりました。
青磁の釉調は、素地や釉薬の成分、また施された釉の厚みにもよって大変種類が多く、その深みのある美しさは古くから多くの人に愛賞されてきた東洋陶磁を代表する陶芸でもあります。
伝統ある窯元生まれ
三浦小平二は1933年、現在の新潟県佐渡市相川に 生まれました。父は無名異焼の三浦小平(三代三浦常山の二男)で、伝統ある窯元に生まれながらにして元々は画家志望でした。そんな父のアドバイスにより、陶芸の技術だけではなく「デッサン力」や「造形力」を体得するべく、1951年に東京芸術大学美術学部彫刻科に入学しました。
生まれました。父は無名異焼の三浦小平(三代三浦常山の二男)で、伝統ある窯元に生まれながらにして元々は画家志望でした。そんな父のアドバイスにより、陶芸の技術だけではなく「デッサン力」や「造形力」を体得するべく、1951年に東京芸術大学美術学部彫刻科に入学しました。
当時教授であった平櫛田中に造形を学び、又、仲間とともに陶磁器研究会をつくり、後の重要無形文化財【色絵磁器】保持者の加藤土師萌に陶芸の指導を受けるなど、意欲的に高度な技を体得しました。
卒業後は父の「一度職人の修行をしてこい」という勧めで、京都の製陶会社や岐阜県陶磁器試験場で土づくりや窯焚きなどの下仕事を体で覚え、多様な陶技を基礎から学びました。
その後、母校に戻り、副手、非常勤講師を務めながら制作の目標を灰釉陶器から鈞窯、青磁へと定めました。
青磁と色絵の融合
 三浦が青磁の制作に取り組むようになったのは1966年頃からで、初めは素地に信楽の土を使っていました。しかし、1972年に台湾の故宮博物院で中国南宋時代の官窯青磁の鉢を観察する機会を得た時、その胎土が故郷佐渡の無名異の土に近似している事を直感したといいます。
三浦が青磁の制作に取り組むようになったのは1966年頃からで、初めは素地に信楽の土を使っていました。しかし、1972年に台湾の故宮博物院で中国南宋時代の官窯青磁の鉢を観察する機会を得た時、その胎土が故郷佐渡の無名異の土に近似している事を直感したといいます。
帰国後は無名異の朱泥土の素地に青磁釉をかけるという独自の青磁技法を開拓し、それまで追求していた中国宋代の青磁とは異なる、三浦独自の青磁の造形世界が創り出されるようになりました。
さらに1980年頃からはもうひとつのテーマを持つようになります。それは青磁と色絵の併用です。西アジアや中国・モンゴルなどを旅行して得たインスピレーションを基に、軽妙なタッチで絵付けを施した青磁など、品格を保ちながらも親しみのある作風へと展開していきました。
東洋古来の青磁の世界に新たな展開を示したことが高く評価され、1997年に「青磁」の分野で初めて重要無形文化財保持者に認定されました。
青磁と絵画的、彫刻的表現が調和して作られる作品は、今でも色あせることなく独特の情緒とロマンを醸し出しています。
|
|
古美術ますけんが選ばれる理由
|
|
|
|
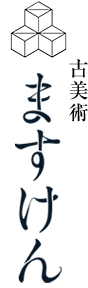
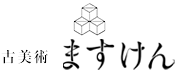
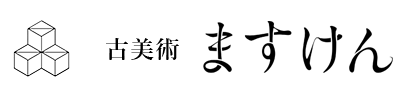
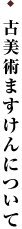
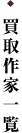
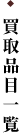
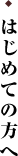
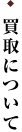
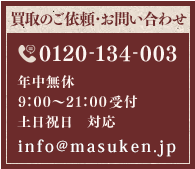
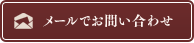
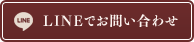






 0120-134-003
0120-134-003 info@masuken.jp
info@masuken.jp ID:@masuken
ID:@masuken
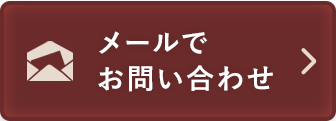
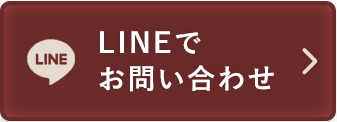
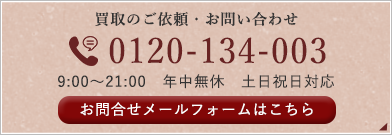
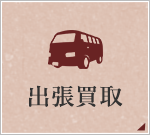
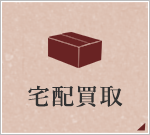

 出張費無料
出張費無料 実績多数
実績多数 安心・信頼
安心・信頼 迅速・丁寧
迅速・丁寧