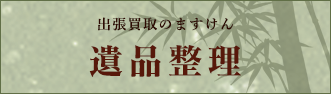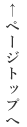コラム
- トップ
- 「ペルシャ陶を現代に蘇らせた 加藤卓男」
-
コラム
「ペルシャ陶を現代に蘇らせた 加藤卓男」2017/06/12
 三彩とは鉛釉を使った二種以上の色釉で染め上げた低火度のやきものです。中国唐時代の唐三彩は華麗な色調で流行し、この影響を受けて日本でも奈良時代に奈良三彩が誕生しました。この「三彩」は、日本において初めて人為的に用いられた最古の釉薬です。しかし非常に高度な技術を要す為、技術者が来日して指導したのではないかといわれています。又、高度な技術を維持するのは困難であったことから、平安期に入ると緑釉だけを掛けて作られる緑釉陶器が主流になっていきました。
三彩とは鉛釉を使った二種以上の色釉で染め上げた低火度のやきものです。中国唐時代の唐三彩は華麗な色調で流行し、この影響を受けて日本でも奈良時代に奈良三彩が誕生しました。この「三彩」は、日本において初めて人為的に用いられた最古の釉薬です。しかし非常に高度な技術を要す為、技術者が来日して指導したのではないかといわれています。又、高度な技術を維持するのは困難であったことから、平安期に入ると緑釉だけを掛けて作られる緑釉陶器が主流になっていきました。
現代になってこの難易度の高い「三彩」の釉薬・焼成方法を8年に渡って研究し、完成させた陶芸家がいます。
1995年に「三彩」の技術保持者として認定された加藤卓男です。
陶芸家 加藤卓男の誕生
1917年、加藤卓男は江戸時代から続く美濃焼窯 元五代加藤幸兵衛の長男として、岐阜県土岐郡市之倉村(現、多治見市市之倉町)に生まれました。加藤と同じ岐阜県多治見市出身の荒川豊蔵が桃山時代の志野の古窯趾発見以来、土岐川流域の丘陵地帯に起こった発掘ブームを見て育ちました。
元五代加藤幸兵衛の長男として、岐阜県土岐郡市之倉村(現、多治見市市之倉町)に生まれました。加藤と同じ岐阜県多治見市出身の荒川豊蔵が桃山時代の志野の古窯趾発見以来、土岐川流域の丘陵地帯に起こった発掘ブームを見て育ちました。
1935年岐阜県立多治見工業学校を卒業後、京都の商工省陶磁器試験所に入所。37年同試験所終業後、帰郷し家業の幸兵衛窯に勤務しました。翌38年より従軍し、転属先の広島市で残留放射能により被爆。10年ほど入退院を繰り返しましたが、54年第10回日展に「黒地緑彩草花文花瓶」を出品し初入選。61年にはフィンランド政府の招きによりフィンランドの工芸美術学校に留学する機会を得ました。
このフィンランドへの留学こそが、その後の陶芸作家としての彼の方向を決定づけたのでした。
ペルシャ陶器との出会い
 加藤は留学中に見た古代ペルシア陶器の斬新な色彩や独創的な造形や釉調に多大な影響を受けました。自らも西アジアで本格的な発掘研究に取り組み、滅び去った幻の名陶ラスター彩の復元や、青釉・三彩・ペルシア色絵などと日本文化の融合に成功し、多彩な作品を発表しました。その一方で、昭和55年に宮内庁正倉院より正倉院三彩の復元制作を委嘱され、約9年の研究の末、「三彩鼓胴」「二彩鉢」を納入。この経験と技術を生かし、自身の創意による三彩の制作活動にも取り組み独自の領域を確立しました。
加藤は留学中に見た古代ペルシア陶器の斬新な色彩や独創的な造形や釉調に多大な影響を受けました。自らも西アジアで本格的な発掘研究に取り組み、滅び去った幻の名陶ラスター彩の復元や、青釉・三彩・ペルシア色絵などと日本文化の融合に成功し、多彩な作品を発表しました。その一方で、昭和55年に宮内庁正倉院より正倉院三彩の復元制作を委嘱され、約9年の研究の末、「三彩鼓胴」「二彩鉢」を納入。この経験と技術を生かし、自身の創意による三彩の制作活動にも取り組み独自の領域を確立しました。
伝統ある窯元で生まれながらも独自の研究でペルシア陶を蘇らせた加藤卓男。そのペルシア陶技は、現在加藤の長男である7代加藤幸兵衛によって受け継がれています。
|
|
古美術ますけんが選ばれる理由
|
|
|
|
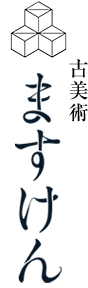
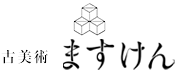
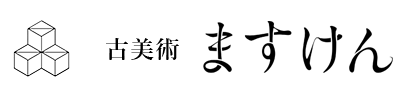
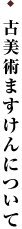
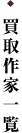
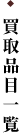
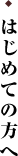
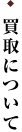
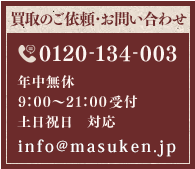
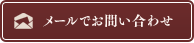
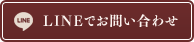






 0120-134-003
0120-134-003 info@masuken.jp
info@masuken.jp ID:@masuken
ID:@masuken
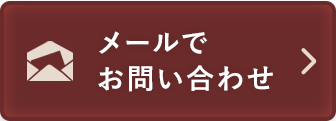
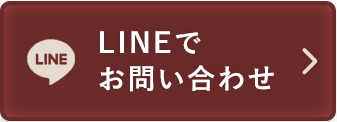
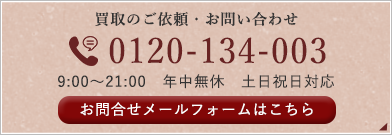
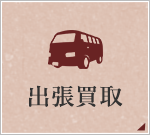
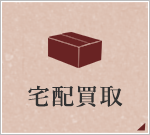

 出張費無料
出張費無料 実績多数
実績多数 安心・信頼
安心・信頼 迅速・丁寧
迅速・丁寧