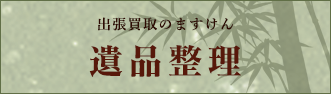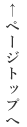コラム
- トップ
- 「逆境を逆手に独自の技を生み出す 鍛金家 関谷四郎」
-
コラム
「逆境を逆手に独自の技を生み出す 鍛金家 関谷四郎」2017/12/25

秋田市に生まれ、帝室技芸員の平田宗幸の高弟であった関谷四郎。晩年は「人間国宝」「紫綬褒章」「勲四等旭日小綬章」を受章するなど、鍛金作家として大成功を収めた人生であった半面、幼少の頃は病弱であった為、人一倍苦労と努力を重ねた作家でもありました。
天職に出会うまで
関谷四郎は1907年(明治40年)、秋田県秋田市 に生まれました。5歳の時に父が亡くなり、その後追い打ちをかけるように小児麻痺にかかりました。後遺症から片足が不自由になり松葉杖をついての生活を強いられる事になった関谷少年。彼の行く先を案じ、手に職を付けさせてあげたいという家族の配慮により、秋田市内の森金銀細工店に弟子入りし、秋田の伝統工芸「銀線細工」を学ぶ事になりました。そして18歳の時に転機が訪れます。秋田県主催の鍛金講習会に参加し、東京から招かれた講師で鍛金家の河内宗明の講習を受けた関谷は、鍛金の造形美術に深い関心を覚えました。早速弟子入りを願い出て、20歳を機に一人上京し、河内宗明の内弟子として鍛金技法を一から学びました。
に生まれました。5歳の時に父が亡くなり、その後追い打ちをかけるように小児麻痺にかかりました。後遺症から片足が不自由になり松葉杖をついての生活を強いられる事になった関谷少年。彼の行く先を案じ、手に職を付けさせてあげたいという家族の配慮により、秋田市内の森金銀細工店に弟子入りし、秋田の伝統工芸「銀線細工」を学ぶ事になりました。そして18歳の時に転機が訪れます。秋田県主催の鍛金講習会に参加し、東京から招かれた講師で鍛金家の河内宗明の講習を受けた関谷は、鍛金の造形美術に深い関心を覚えました。早速弟子入りを願い出て、20歳を機に一人上京し、河内宗明の内弟子として鍛金技法を一から学びました。
苦情から生まれた接合わせ
 弟子入りした直後から、師は関谷に本格的な鍛金の仕事をさせました。そして東京で鍛金の世界に入って以来、病弱だったのが嘘のように元気になり、他の弟子達の何倍もの仕事量をこなし、卓越した技術を身に着けました。1931年に日本鍛金協会展に出品し、銀賞を受賞。1938年には独立して東京板橋区に工房を移し、鍛金の中でも至難といわれる「接合わせ」の技術を修得。この接合わせは、鍛金技法の特徴である金属塊を叩いて造形する際の、金属を叩く音がうるさいと近所の住民に言われた事がきっかけで、どうしたら音を出さずに制作できるかを考え至った技法です。この技法でもって関谷独自の作風が確立すると、第9回日本伝統工芸展に出品した「鉄ハギ合セ壺」は入選し、斬新な意匠に注目が集まりました。そして第12回伝統工芸展では洗練された幾何学文様と、表面の質感を特色とする斬新な作風を示し、見事奨励賞を受賞しました。その後も日本伝統工芸展に受賞を重ね、1974年紫綬褒章、1977年重要無形文化財保持者「鍛金」に認定、1980年勲4等旭日小綬章を受章しました。
弟子入りした直後から、師は関谷に本格的な鍛金の仕事をさせました。そして東京で鍛金の世界に入って以来、病弱だったのが嘘のように元気になり、他の弟子達の何倍もの仕事量をこなし、卓越した技術を身に着けました。1931年に日本鍛金協会展に出品し、銀賞を受賞。1938年には独立して東京板橋区に工房を移し、鍛金の中でも至難といわれる「接合わせ」の技術を修得。この接合わせは、鍛金技法の特徴である金属塊を叩いて造形する際の、金属を叩く音がうるさいと近所の住民に言われた事がきっかけで、どうしたら音を出さずに制作できるかを考え至った技法です。この技法でもって関谷独自の作風が確立すると、第9回日本伝統工芸展に出品した「鉄ハギ合セ壺」は入選し、斬新な意匠に注目が集まりました。そして第12回伝統工芸展では洗練された幾何学文様と、表面の質感を特色とする斬新な作風を示し、見事奨励賞を受賞しました。その後も日本伝統工芸展に受賞を重ね、1974年紫綬褒章、1977年重要無形文化財保持者「鍛金」に認定、1980年勲4等旭日小綬章を受章しました。
ハンディを苦にせず、逆境であればあるほど実力を発揮する精神力。松葉杖をつきながらも、時には弟子達が走らなければ追いつけない程元気に歩いたという関谷四郎は、鍛金の指導者として後進の育成にも尽力しました。
古美術ますけんでは「関谷四郎」の作品の買取をしております。売却をご検討でしたらフリーダイヤル0120-134-003 又はフォームにてお気軽にお問い合わせ下さい。
|
|
古美術ますけんが選ばれる理由
|
|
|
|
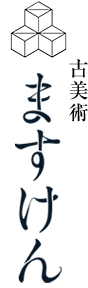
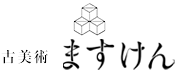
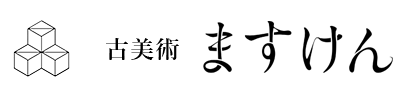
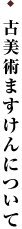
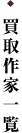
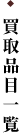
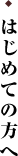
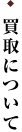
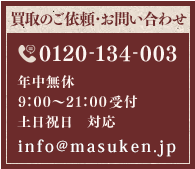
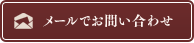
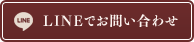






 0120-134-003
0120-134-003 info@masuken.jp
info@masuken.jp ID:@masuken
ID:@masuken
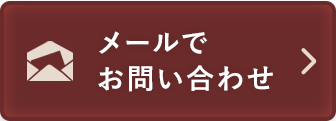
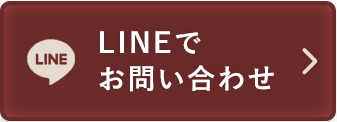
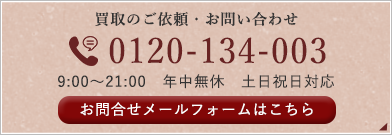
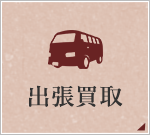
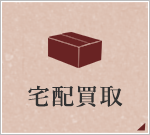

 出張費無料
出張費無料 実績多数
実績多数 安心・信頼
安心・信頼 迅速・丁寧
迅速・丁寧