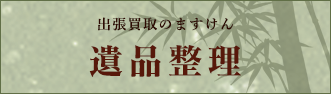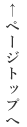コラム
- トップ
- 「玉川堂から独自の木目金技術へ 玉川宣夫」
-
コラム
「玉川堂から独自の木目金技術へ 玉川宣夫」2018/02/19
 海外でも「MOKUMEGANE」の名で知られる鍛金の技法「木目金」。異なる種類の金属板を2・30枚積み重ね、叩いて板状にしたものを部分的に表面を削り落としてさらに叩き込み、木目調の金属板にし、器状に成型していく技法です。この木目金を作り上げるには、気の遠くなるような作業に耐えうる精神力と、完成時の模様を予想しながら削る熟練度が求められます。この非常に高度な技術を独自に研究し、重要無形文化財に認定された作家が、玉川宣夫です。
海外でも「MOKUMEGANE」の名で知られる鍛金の技法「木目金」。異なる種類の金属板を2・30枚積み重ね、叩いて板状にしたものを部分的に表面を削り落としてさらに叩き込み、木目調の金属板にし、器状に成型していく技法です。この木目金を作り上げるには、気の遠くなるような作業に耐えうる精神力と、完成時の模様を予想しながら削る熟練度が求められます。この非常に高度な技術を独自に研究し、重要無形文化財に認定された作家が、玉川宣夫です。
玉川堂5代目に養子入り
玉川宣夫は1942年、新潟県に生まれ、中学 1年生の時に燕市内の「玉川堂」に養子として入りました。玉川堂は江戸時代より鎚起銅器の製法を継承しており、玉川宣夫はここで玉川堂5代目の玉川覚平に師事し、鎚起銅器の伝統技法を修得。21歳の時に金工家の関谷四郎の作品に感銘を受け、弟子入りを志願。二年間関谷のもとで内弟子として修業し、1969年第16回日本伝統工芸展に初入選を果たします。しかし、入選はしても入賞まで辿り着けなかったことから、当時まだ取り組む金工家が少なかった「木目金」に目を向け独自に研究。1982年、第29回日本伝統工芸展で「木目金花瓶」を出品し、NHK会長賞を受賞すると、作品を文化庁へ納入しました。
1年生の時に燕市内の「玉川堂」に養子として入りました。玉川堂は江戸時代より鎚起銅器の製法を継承しており、玉川宣夫はここで玉川堂5代目の玉川覚平に師事し、鎚起銅器の伝統技法を修得。21歳の時に金工家の関谷四郎の作品に感銘を受け、弟子入りを志願。二年間関谷のもとで内弟子として修業し、1969年第16回日本伝統工芸展に初入選を果たします。しかし、入選はしても入賞まで辿り着けなかったことから、当時まだ取り組む金工家が少なかった「木目金」に目を向け独自に研究。1982年、第29回日本伝統工芸展で「木目金花瓶」を出品し、NHK会長賞を受賞すると、作品を文化庁へ納入しました。
木目金技術の第一人者
 最初の入賞から4年後の第33回日本伝統工芸展では「銀、銅、赤銅」を溶接し叩きだして作り上げた「木目金花瓶」を出品すると、東京都知事賞を受賞。
最初の入賞から4年後の第33回日本伝統工芸展では「銀、銅、赤銅」を溶接し叩きだして作り上げた「木目金花瓶」を出品すると、東京都知事賞を受賞。
以降精力的に作品を発表するとともに、玉川宣夫が作り出す多彩な木目模様は高い評価受け、2002年紫綬褒章、2010年重要無形文化財認定、2012年には旭日小綬章を受章しました。
現代では機械でプレスしてしまえば簡単に複数枚の板金を圧縮できてしますが、敢えて「叩いて伸ばす」という昔からのやり方をとり、伝統を守り続けるところに人間国宝としての気位が感じられます。
そして現在でも木目金技術の第一人者として、木目金の伝承と振興に力を尽くしています。
古美術ますけんでは「玉川宣夫」の作品の買取をしております。売却をご検討でしたらフリーダイヤル0120-134-003 又はフォームにてお気軽にお問い合わせ下さい。
|
|
古美術ますけんが選ばれる理由
|
|
|
|
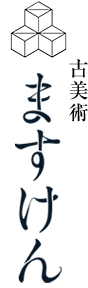
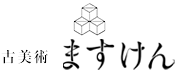
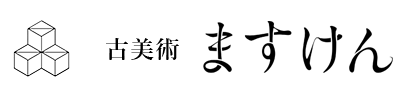
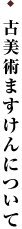
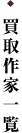
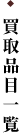
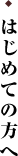
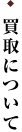
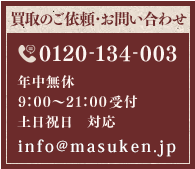
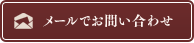
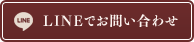






 0120-134-003
0120-134-003 info@masuken.jp
info@masuken.jp ID:@masuken
ID:@masuken
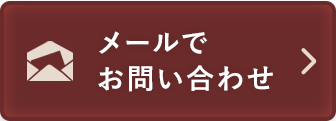
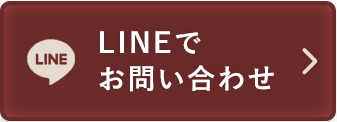
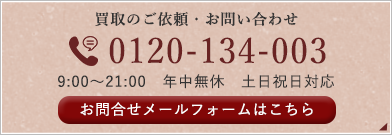
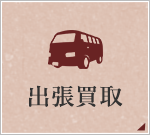
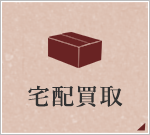

 出張費無料
出張費無料 実績多数
実績多数 安心・信頼
安心・信頼 迅速・丁寧
迅速・丁寧