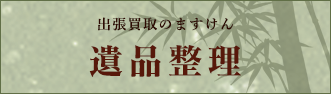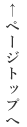コラム
- トップ
- 「急須の価値を高めた 三代山田常山」
-
コラム
「急須の価値を高めた 三代山田常山」2017/06/26

急須といえば常滑焼。
常滑焼といえば急須。
「急須」もしくは「常滑焼」といわれると、滑らかな表面の朱色の急須を思い浮かべる人が少なくないと思います。自らが持っていなくても、実家や親せきの家の食卓に、空気のように自然と溶け込んでいる風景が目に浮かぶ人もいる事でしょう。日本人にとっての「お茶」は、着物を着て抹茶碗でいただく「お抹茶」より、普段着で日常に飲む「煎茶」を指す事の方が圧倒的に多く、煎茶を入れる為の急須はお鍋やフライパンと同じ位、生活に欠かせない道具でした。
その日常の道具、「急須」の価値を高めようと、生涯にわたって急須一筋に歩み続けた陶芸家がいます。常滑に生まれ常滑で育った三代山田常山。彼は日本で初めて「常滑焼(急須)」で人間国宝に認定された陶芸家でもあります。
常滑生まれ、常滑育ち
三代山田常山は、1924年(大正13年) に愛知県常滑市に生まれました。祖父は朱泥茶器の名工と言われた初代山田常山、父は二代常山で、少年の頃から二人の名工に基礎的な陶技を学び、中学に入る頃には轆轤による急須作りを始めていました。おそらく物心がついた頃から、進路は常滑急須作りに決まっていたのでしょう。1941年に愛知県立常滑工業学校窯業科を卒業。1961年に父二代常山の死去により、三代山田常山を襲名。1958年(昭和33年)第5回日本工芸展で初入選を果たしました。この時、同じく入選したのは「色絵磁器」の酒井田柿右衛門や加藤土師萌、備前焼の金重陶窯、萩焼の三輪壽雪、鉄釉陶器の石黒宗麿など、後の人間国宝となる豪華な顔ぶれ、作品も「茶道具」や「壺」「鉢」などのどちらかというと鑑賞用のものばかり。そんな中、愛知県からの入選は三代常山ただ一人で、それも出品した作品は、生活の一道具である朱泥の急須でした。
に愛知県常滑市に生まれました。祖父は朱泥茶器の名工と言われた初代山田常山、父は二代常山で、少年の頃から二人の名工に基礎的な陶技を学び、中学に入る頃には轆轤による急須作りを始めていました。おそらく物心がついた頃から、進路は常滑急須作りに決まっていたのでしょう。1941年に愛知県立常滑工業学校窯業科を卒業。1961年に父二代常山の死去により、三代山田常山を襲名。1958年(昭和33年)第5回日本工芸展で初入選を果たしました。この時、同じく入選したのは「色絵磁器」の酒井田柿右衛門や加藤土師萌、備前焼の金重陶窯、萩焼の三輪壽雪、鉄釉陶器の石黒宗麿など、後の人間国宝となる豪華な顔ぶれ、作品も「茶道具」や「壺」「鉢」などのどちらかというと鑑賞用のものばかり。そんな中、愛知県からの入選は三代常山ただ一人で、それも出品した作品は、生活の一道具である朱泥の急須でした。
その後の三代常山は、この日本伝統工芸展を中心に活動を展開しましたが、急須に対する劣等感から、「朱泥」ではなく「紫泥」や「烏泥」、「自然釉」の急須を出品するようになります。しかしそれは「朱泥の急須」をただ投げ出してしまったのではありません。常々「朱泥急須の価値を高めたい」、そう考えながら技の向上や技法の開発など、作品としての完成度を高める事を課題として取り組んでいたのでした。
朱泥急須、再び復活
 三代常山が再び日本工芸展(1999年)に朱泥急須を出品したのは、最初の出品から実に41年ぶりの事でした。長い間封印してきた朱泥急須の出品、一体どんな心境の変化があったのでしょうか。
三代常山が再び日本工芸展(1999年)に朱泥急須を出品したのは、最初の出品から実に41年ぶりの事でした。長い間封印してきた朱泥急須の出品、一体どんな心境の変化があったのでしょうか。
-答えは前年にありました。
1998年、三代常山は日本で初めて「常滑焼」、それも「急須」の分野で重要無形文化財保持者に認定されたのです。
人間国宝の認定において、特に陶芸部門の指定名称で、器種を特定しての認定はそれまで前例がありませんでした。今でも三代常山ただ一人という、非常にレアなケースでの認定です。三代常山自身も、自分が人間国宝に認定されるなど考えていなかったようで、文化庁から認定の連絡があった時は冷静にふるまいながらも、心の中では心底喜んでいました。
又、41年もの間、三代常山は素地となる土の調整や轆轤形成、焼成、仕上に至る一貫制作のすべての技法を高度に体得し、急須の形や表面の装飾でも多彩なバリエーションを展開。さらに見た目だけでなく、最後の一滴までお茶を楽しむ事ができるキレのよさなどの使い勝手も徹底的に追究。そうして生まれた「実用性と機能性を兼ね備えた美しい道具」こそ、三代常山が長年追い求めてきたものなのでした。
41年ぶりの朱泥急須の出品は、人間国宝としての自覚、そして手作り急須の伝統を守り伝えてきた三代常山のさらなる出発を意味するメッセージが、強く込められていたのです。
|
|
古美術ますけんが選ばれる理由
|
|
|
|
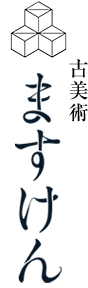
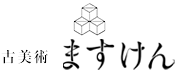
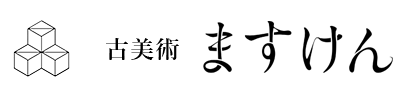
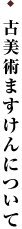
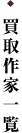
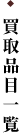
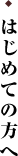
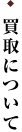
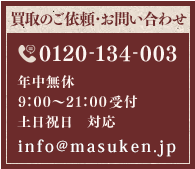
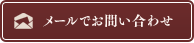
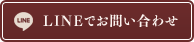






 0120-134-003
0120-134-003 info@masuken.jp
info@masuken.jp ID:@masuken
ID:@masuken
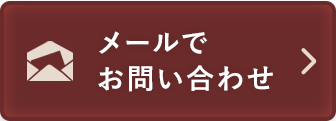
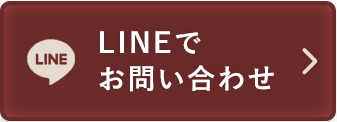
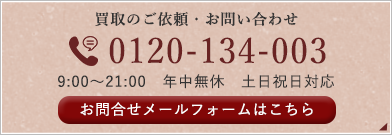
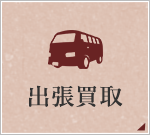
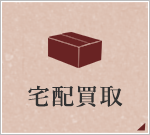

 出張費無料
出張費無料 実績多数
実績多数 安心・信頼
安心・信頼 迅速・丁寧
迅速・丁寧