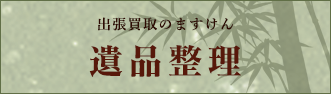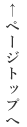コラム
- トップ
- 「布目象嵌を深化 彫金家 鹿島一谷」
-
コラム
「布目象嵌を深化 彫金家 鹿島一谷」2017/09/11
 鹿島一谷は曾祖父の代から続く布目象嵌を専門とする彫金の家に生まれ、最後まで彫金家としての人生を歩みました。彫金本来の造形美を追い求め、それを世に示すことで、それまで技術中心であった彫金の価値観を覆しました。
鹿島一谷は曾祖父の代から続く布目象嵌を専門とする彫金の家に生まれ、最後まで彫金家としての人生を歩みました。彫金本来の造形美を追い求め、それを世に示すことで、それまで技術中心であった彫金の価値観を覆しました。
彫金家四代目
鹿島一谷は1898年、東京都下谷区(現台東区)
 に鹿島一谷光敬の長男として生まれました。14歳で彫金家関口一也・真也父子に師事し、彫金・象嵌・色絵・台付・着色・鑞付・合金配合法等を学びました。20歳の時に父が他界したために家督を継ぎ、帯留や簪などの装身具を手掛けるようになりました。しかし、ただ同じ形を作るだけのいわゆる「数もの」に飽き足らなくなった鹿島は、水指や花入といった器ものに取り組むようになり、帝展などで出品するようになりました。
に鹿島一谷光敬の長男として生まれました。14歳で彫金家関口一也・真也父子に師事し、彫金・象嵌・色絵・台付・着色・鑞付・合金配合法等を学びました。20歳の時に父が他界したために家督を継ぎ、帯留や簪などの装身具を手掛けるようになりました。しかし、ただ同じ形を作るだけのいわゆる「数もの」に飽き足らなくなった鹿島は、水指や花入といった器ものに取り組むようになり、帝展などで出品するようになりました。
戦後は海野清や北原千鹿に指導を受けるようになると、工芸表現の造詣を深め、金属そのものの性質を充分に生かした作品を手掛けるようになりました。
布目象嵌の深化
 布目象嵌とは、素地となる金属の表面に目切鏨で縦・横・斜めに布目状の筋を切って、その上から他の薄い金属を木槌などで叩き込んで張り付ける金属の加飾技法の一つです。元々はポルトガル人によって持ち込まれ、鉄砲に施された装飾起源説が有力です。「鉄地への金銀装飾技術」は流行し、武器・武具へ広く応用されましたが、明治9年の「廃刀令」によって武器・武具への需要が減衰。以降装飾品や美術工芸品にその技術が転用されるようになりました。
布目象嵌とは、素地となる金属の表面に目切鏨で縦・横・斜めに布目状の筋を切って、その上から他の薄い金属を木槌などで叩き込んで張り付ける金属の加飾技法の一つです。元々はポルトガル人によって持ち込まれ、鉄砲に施された装飾起源説が有力です。「鉄地への金銀装飾技術」は流行し、武器・武具へ広く応用されましたが、明治9年の「廃刀令」によって武器・武具への需要が減衰。以降装飾品や美術工芸品にその技術が転用されるようになりました。
鹿島一谷は家伝の布目象嵌をさらに深化させ、グレーの濃淡の表現を可能にし、あたかも薄墨で描いたかのような優雅で洗練された作品を生み出す事に成功しました。1957年には記録作成等の措置を投ずるべき無形文化財布目象嵌の技術者として選択され、1964年唐招提寺蔵国宝金亀舎利塔保存修理、1965年山形県天童市若松寺重要文化財金銅観音像懸仏保存修理に従事するなど、日本の重要な彫金家としての地位を築き上げました。
|
|
古美術ますけんが選ばれる理由
|
|
|
|
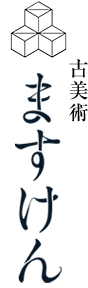
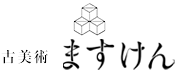
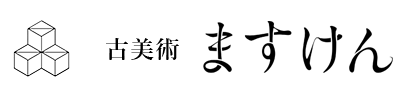
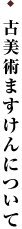
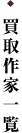
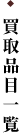
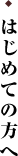
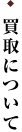
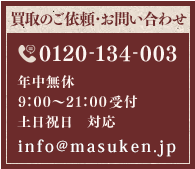
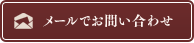
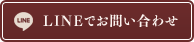






 0120-134-003
0120-134-003 info@masuken.jp
info@masuken.jp ID:@masuken
ID:@masuken
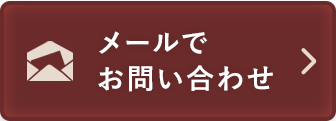
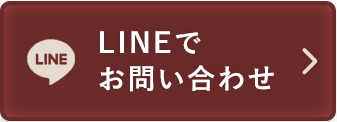
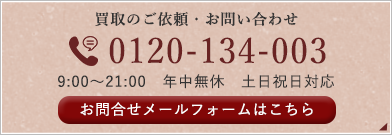
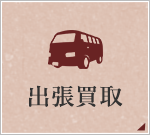
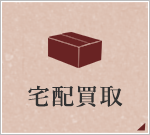

 出張費無料
出張費無料 実績多数
実績多数 安心・信頼
安心・信頼 迅速・丁寧
迅速・丁寧