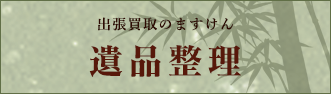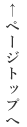コラム
- トップ
- 「江戸時代から続く肥後象嵌を継承 米光光正」
-
コラム
「江戸時代から続く肥後象嵌を継承 米光光正」2018/01/15

「肥後もっこす」
一度決めたら決して曲げない。頑固一徹。武骨な熊本県の県民性を表した言葉です。
肥後象嵌を極め、「肥後象嵌・透」の技術保持者として人間国宝に認定された米光光正は、激動の時代を耐え抜き、15歳から80年近い年月を「肥後象嵌・透」一筋で歩んできた、正に「肥後もっこす」な性格の金工家でした。
江戸時代の名工 林又七に迫る
米光光正は1888年、母の実家である熊本県坪井の 田辺家で生まれました。幼い時に父と死別し、15歳から祖父で金工家の田辺保平と、母の弟で同じく金工家の吉太郎に師事。熊本に旧藩時代から伝わっている「肥後象嵌」の技法を修得する傍ら、月一回の休みには絵画や書道、生け花なども学び、教養を深めました。
田辺家で生まれました。幼い時に父と死別し、15歳から祖父で金工家の田辺保平と、母の弟で同じく金工家の吉太郎に師事。熊本に旧藩時代から伝わっている「肥後象嵌」の技法を修得する傍ら、月一回の休みには絵画や書道、生け花なども学び、教養を深めました。
田辺家は刀装具金工の家系で、初代清次郎・2代目保平(祖父)・3代目吉太郎(叔父)と続いており、江戸時代初期より九州肥後を中心に繁栄した肥後金工の技法を継承。肥後金工の主流派には林・平田・西垣・志水の4派があり、中でも林派の始祖、林又七は加藤清正に従って肥後に移住した鐔工で、精緻な透かし彫りと洗練された金布象嵌などを施し、装剣小道具を芸術の域まで引き上げた江戸時代の名工です。この又七の作品に感銘を受けた米光光正は、又七の研究に明け暮れ、又七鐔の端正な造形と高度な透かし彫りや象嵌の意匠などを高度に体得。1918年頃より1937年にかけて商工会主催の全国工芸展にたびたび入選し、40歳代で独立しました。
激動の時代を生き抜いた鐔工
 戦時中は金地金の使用を禁じられ、軍需工場に徴用されたりもしましたが、根っからの「肥後もっこす」の精神でどんな苦境にも耐え抜きました。やがて長かった激動の時代は終わり、平和な世の中が戻ってくると、さらにその腕に磨きをかけ、1959年には熊本県無形文化財に指定、1965年は重要無形文化財「肥後象嵌・透」の技術保持者として人間国宝の認定。さらに翌年には勲五等旭日章を受章しました。米光78歳の時でした。この頃から円熟期に入ったと評され、86歳の時に制作した「八木瓜形鉄地八つ蕨手透二重唐草象嵌鐔」(※画像参照)は、円熟の極みといえる会心作で、表裏全体に緻密な唐草模様を金象嵌で流麗に施されています。
戦時中は金地金の使用を禁じられ、軍需工場に徴用されたりもしましたが、根っからの「肥後もっこす」の精神でどんな苦境にも耐え抜きました。やがて長かった激動の時代は終わり、平和な世の中が戻ってくると、さらにその腕に磨きをかけ、1959年には熊本県無形文化財に指定、1965年は重要無形文化財「肥後象嵌・透」の技術保持者として人間国宝の認定。さらに翌年には勲五等旭日章を受章しました。米光78歳の時でした。この頃から円熟期に入ったと評され、86歳の時に制作した「八木瓜形鉄地八つ蕨手透二重唐草象嵌鐔」(※画像参照)は、円熟の極みといえる会心作で、表裏全体に緻密な唐草模様を金象嵌で流麗に施されています。
肥後象嵌を代表する名工・林又七を目標に精進し、15歳から80年近い年月を「肥後象嵌・透」一筋で歩んできた米光光正。そんな米光を「生涯職人気質に徹した肥後もっこす」と評する人もいるほど徹底した気骨な鐔工は、日本の金工史に多大な功績を残しました。
古美術ますけんでは「米光光正」の作品の買取をしております。売却をご検討でしたらフリーダイヤル0120-134-003 又はフォームにてお気軽にお問い合わせ下さい。
|
|
古美術ますけんが選ばれる理由
|
|
|
|
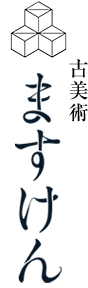
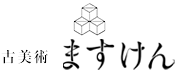
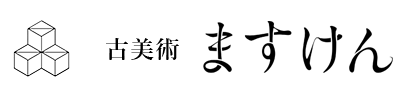
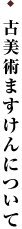
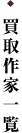
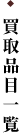
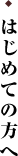
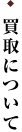
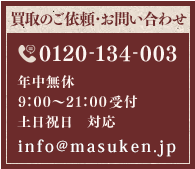
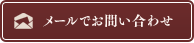
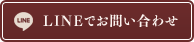






 0120-134-003
0120-134-003 info@masuken.jp
info@masuken.jp ID:@masuken
ID:@masuken
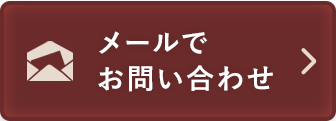
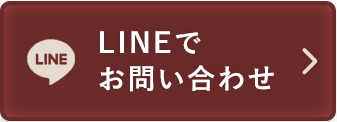
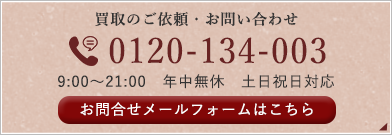
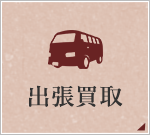
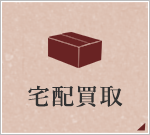

 出張費無料
出張費無料 実績多数
実績多数 安心・信頼
安心・信頼 迅速・丁寧
迅速・丁寧