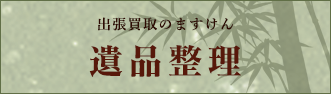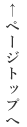コラム
- トップ
- 「豪壮華麗な刀作り 高橋貞次」
-
コラム
「豪壮華麗な刀作り 高橋貞次」2018/01/29

刀工の納得できる刀は年間数本が限度、ましてや大作ともなれば一本を作り上げるのに数年はかかると言われています。なぜ刀工はそこまでこだわるのか・・・。答えは「魂を込めて作り上げた作品」に、自分の銘を切るからです。自分の作品が後世に残る限り、刀工の名も評価され続けます。だから刀工は己の持ちうる技術と精神の限りを刀に注ぐのです。
備前伝と相州伝
 「日本刀」の分野で初めて人間国宝に認定された高橋貞次は、「五ヶ伝」と言われる5種類の各鍛法に精通し、特に備前伝と相州伝を多く制作しました。貞次の備前伝は太刀・刀ともに反りが強い腰反りで、地肌は板目が詰んで精美であり、刃文は華やかな「丁子乱れ」。一方の相州伝(※画像参照)は、鎌倉時代の相模国正宗・貞宗の作風を研究し、それらの写し等を制作。表面にきらきらと光る微粒子が現れる「地沸(じにえ)」がつき、さらに網状の「地景(ちけい)」や、斑状の「地斑(じふ)」が現れ、刃文は丸い碁石の連続のような「互の目乱」といったように、独自の個性を表現していながら、相州伝の特色をよく捉えており高く評価されました。
「日本刀」の分野で初めて人間国宝に認定された高橋貞次は、「五ヶ伝」と言われる5種類の各鍛法に精通し、特に備前伝と相州伝を多く制作しました。貞次の備前伝は太刀・刀ともに反りが強い腰反りで、地肌は板目が詰んで精美であり、刃文は華やかな「丁子乱れ」。一方の相州伝(※画像参照)は、鎌倉時代の相模国正宗・貞宗の作風を研究し、それらの写し等を制作。表面にきらきらと光る微粒子が現れる「地沸(じにえ)」がつき、さらに網状の「地景(ちけい)」や、斑状の「地斑(じふ)」が現れ、刃文は丸い碁石の連続のような「互の目乱」といったように、独自の個性を表現していながら、相州伝の特色をよく捉えており高く評価されました。
古武士の気概
 戦後は刀剣制作が禁止されたため、再び制作できるようになるまで専ら古刀剣の研究をして過ごしました。そして1955年、古刀剣研究の成果が実を結びます。日本美術刀剣保存協会主催の第1回「作刀技術発表会」において、備前長舟景光作の国宝「小龍影光」を写した太刀が見事に特選大一席を得たのです。さらに、4か月後には人間国宝にも選ばれ、1959年には皇太子(後の平成天皇)御成婚に際し美智子妃殿下の御守刀を、その後も浩宮・礼宮にも御守刀制作の用命を受けるなどしました。
戦後は刀剣制作が禁止されたため、再び制作できるようになるまで専ら古刀剣の研究をして過ごしました。そして1955年、古刀剣研究の成果が実を結びます。日本美術刀剣保存協会主催の第1回「作刀技術発表会」において、備前長舟景光作の国宝「小龍影光」を写した太刀が見事に特選大一席を得たのです。さらに、4か月後には人間国宝にも選ばれ、1959年には皇太子(後の平成天皇)御成婚に際し美智子妃殿下の御守刀を、その後も浩宮・礼宮にも御守刀制作の用命を受けるなどしました。
恵まれた才能と旺盛な研究心により五ヶ伝に通じ、国宝の太刀「景光」を始め名物を写して往年の名匠の作域に迫った高橋貞次。享年66歳で亡くなる年まで、精力的に刀剣制作に身を投じました。
古美術ますけんでは「高橋貞次」の作品の買取をしております。売却をご検討でしたらフリーダイヤル0120-134-003 又はフォームにてお気軽にお問い合わせ下さい。
|
|
古美術ますけんが選ばれる理由
|
|
|
|
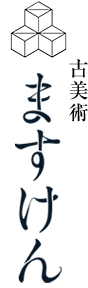
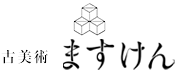
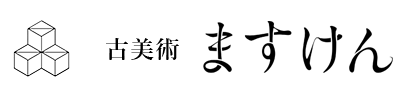
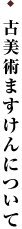
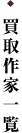
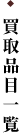
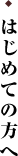
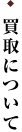
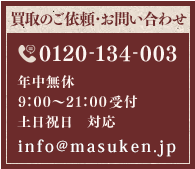
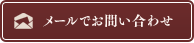
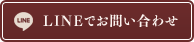






 0120-134-003
0120-134-003 info@masuken.jp
info@masuken.jp ID:@masuken
ID:@masuken
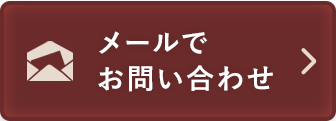
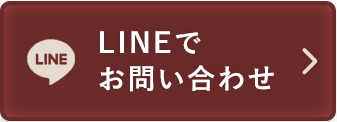
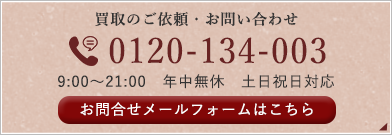
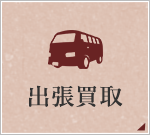
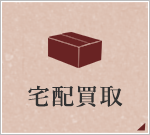

 出張費無料
出張費無料 実績多数
実績多数 安心・信頼
安心・信頼 迅速・丁寧
迅速・丁寧