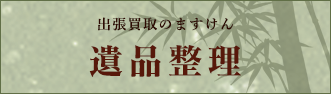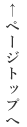コラム
- トップ
- 「桃山陶の通説を覆した荒川豊蔵」
-
コラム
「桃山陶の通説を覆した荒川豊蔵」2017/01/16

志野焼は桃山時代の天正・文禄の頃に美濃で生まれた日本独自のやきものです。もぐさ土という柔らかい土を使い、筆で絵付けをして長石釉を掛けて焼いた日本で最初の白い陶器といわれています。当時茶の湯で大流行したのにもかかわらず、短い期間のうちに生産効率の問題などから衰退し、400年もの間途絶えていたという謎の多いやきものでもあります。その志野の再現に、人間国宝の荒川豊蔵が取り組む最初のきっかけとなったのは、1930年の「志野筍絵筒茶碗」との出会いがあったからでした。
志野筍絵筒茶碗との出会い
製陶の町として知られる岐阜県多治見市に生まれた 荒川豊蔵は、28歳の時に画家を志して上京するも断念。その後縁あって京都の宮永東山窯に工場長として勤めていました。この東山窯を訪ねてきた北大路魯山人が会員制の高級料亭星ヶ丘茶寮で使う食器を造るため、鎌倉に星ヶ丘窯を設け、その窯場主任として迎えられました。
荒川豊蔵は、28歳の時に画家を志して上京するも断念。その後縁あって京都の宮永東山窯に工場長として勤めていました。この東山窯を訪ねてきた北大路魯山人が会員制の高級料亭星ヶ丘茶寮で使う食器を造るため、鎌倉に星ヶ丘窯を設け、その窯場主任として迎えられました。
1930年、星ヶ丘窯の展覧会が名古屋で開かれたとき、その展覧会で筍の絵のある志野筒茶碗を見る機会を得ました。それまでは志野をはじめ瀬戸黒・黄瀬戸・織部といった桃山陶は瀬戸産とされていましたが、この通説に疑問を抱いた豊蔵は、翌々日岐阜県可児市大萱の山中で同じ筍が描かれた志野の陶片を発見し、これまでの通説を覆し陶芸界にも衝撃が走りました。
この世紀の大発見を契機に魯山人のもとを離れ、陶片発見の地で桃山陶の再現に取り組むようになった豊蔵ですが、窯の構築から陶土、釉薬、そして制作技術まで再現していくというのは想像を絶する程の苦難の道のりでありました。
日本初の人間国宝
1932年、豊蔵は大萱牟田洞に移築し陶房を作りました。飲み水は小川から運び、ガス、冷蔵庫、洗濯機、車もない、一見不便と思われる環境に敢えて身を置く事で、少しでも桃山期に近づこうとしたのかも知れません。当時の美濃では熱効率がよく大量生産が可能な連房式登窯が主流でしたが、「桃山の志野」にこだわった豊蔵は、窯でさえも 桃山と同じ半地下式大窯を築き、とことん桃山期の制作工程や窯を追求しました。そうして手探りでなんとか漕ぎつけた初窯はあえなく失敗。それでも古窯跡に残る陶片を手がかりに試行錯誤を重ね、少しずつ桃山陶に近づいていき、1955年、ついには第一回重要無形文化財の認定で志野と瀬戸黒の2分野で選ばれる程になりました。ちなみにこの時の認定で2分野の指定を受けたのは豊蔵のみで、さらに日本の伝統的な陶技の技術という分野から選ばれたのも、豊蔵の志野と瀬戸黒という美濃の桃山陶だけでした。
桃山と同じ半地下式大窯を築き、とことん桃山期の制作工程や窯を追求しました。そうして手探りでなんとか漕ぎつけた初窯はあえなく失敗。それでも古窯跡に残る陶片を手がかりに試行錯誤を重ね、少しずつ桃山陶に近づいていき、1955年、ついには第一回重要無形文化財の認定で志野と瀬戸黒の2分野で選ばれる程になりました。ちなみにこの時の認定で2分野の指定を受けたのは豊蔵のみで、さらに日本の伝統的な陶技の技術という分野から選ばれたのも、豊蔵の志野と瀬戸黒という美濃の桃山陶だけでした。
美濃の山中で常に桃山と向かい合い、桃山の再興に尽力した豊蔵は、いつしか桃山を超えて独自の芸術へと到達し、晩年は得意な絵画を生かした色絵や染付による飾り皿など、独自の造形美と色彩美を誇る作品を生み出しました。
|
|
古美術ますけんが選ばれる理由
|
|
|
|
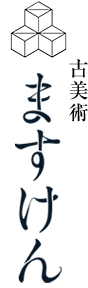
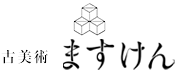
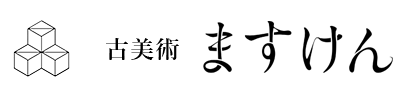
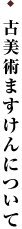
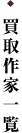
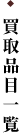
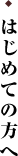
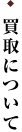
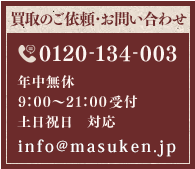
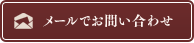
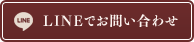






 0120-134-003
0120-134-003 info@masuken.jp
info@masuken.jp ID:@masuken
ID:@masuken
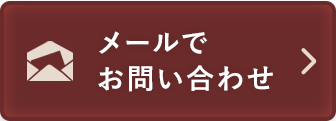
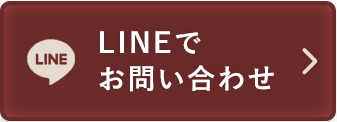
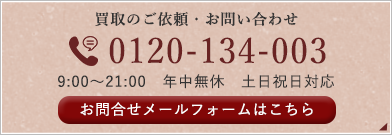
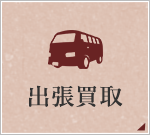
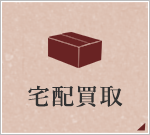

 出張費無料
出張費無料 実績多数
実績多数 安心・信頼
安心・信頼 迅速・丁寧
迅速・丁寧