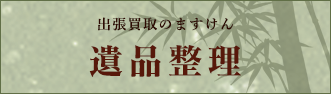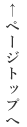コラム
- トップ
- 「小さな世界に技のすべてを凝縮 鴨下春明」
-
コラム
「小さな世界に技のすべてを凝縮 鴨下春明」2017/10/16
 彫金は近世以来、鍔(つば)や目貫などの刀剣の拵を装飾する金具の制作技術として高度に発達した伝統的な金工技術です。こうした装剣金具は刀剣の隆盛とともに発達していきましたが、明治初期の廃刀令以後は多くの刀工達と同様、装剣金具師達の多くも行き場を失いました。しかし金具師達は帯留や飾り金具などの装飾金具に活路を見出し、新しい時代に対応した彫金工芸を創り出していくようになりました。
彫金は近世以来、鍔(つば)や目貫などの刀剣の拵を装飾する金具の制作技術として高度に発達した伝統的な金工技術です。こうした装剣金具は刀剣の隆盛とともに発達していきましたが、明治初期の廃刀令以後は多くの刀工達と同様、装剣金具師達の多くも行き場を失いました。しかし金具師達は帯留や飾り金具などの装飾金具に活路を見出し、新しい時代に対応した彫金工芸を創り出していくようになりました。
大正生まれの鴨下春明も、独創的なデザインと緻密な技術を駆使し、数センチ四方の小さな作品の中に自然に生きる動植物を見事に表現した金具師です。
江戸金工の彫金家・桂光春に師事
鴨下春明は1915年、東京に生まれました。高等小学校を卒業後は伯父であり江戸金工の流れを汲む彫金家・桂光春に師事 し、伝統的な彫金技法を高度に体得、技の錬磨に力を注ぎました。1940年に独立して作家生活に入りますが、時は太平洋戦争真っただ中であったため、戦後になってから日展に出品するようになりました。1949年・50年と続けて彫金の壺などで作品の入選を果たし、そして1965年、第12回日本工芸展に出品。以降同展や日本伝統金工展、伝統工芸新作展などに小金具などを中心に出品し、持ち味を存分に発揮して受賞を重ねました。
し、伝統的な彫金技法を高度に体得、技の錬磨に力を注ぎました。1940年に独立して作家生活に入りますが、時は太平洋戦争真っただ中であったため、戦後になってから日展に出品するようになりました。1949年・50年と続けて彫金の壺などで作品の入選を果たし、そして1965年、第12回日本工芸展に出品。以降同展や日本伝統金工展、伝統工芸新作展などに小金具などを中心に出品し、持ち味を存分に発揮して受賞を重ねました。
自然界の動植物を見事に表現
 東京の都心部に住んでいた鴨下にとって作品のモチーフにする自然界の動植物を手に入れるのは中々至難の業でした。その為、時に近郊の畑に出向いて果物や野菜を写生したり、銚子や三浦海岸で魚介類を分けてもらい、家に持ち帰って観察したりしていました。特に娯楽を持たなかった鴨下にとって、それは小さな楽しみでもあり、小さいながらも躍動感ある動植物の作品制作へと繋がる重要な架け橋でもありました。
東京の都心部に住んでいた鴨下にとって作品のモチーフにする自然界の動植物を手に入れるのは中々至難の業でした。その為、時に近郊の畑に出向いて果物や野菜を写生したり、銚子や三浦海岸で魚介類を分けてもらい、家に持ち帰って観察したりしていました。特に娯楽を持たなかった鴨下にとって、それは小さな楽しみでもあり、小さいながらも躍動感ある動植物の作品制作へと繋がる重要な架け橋でもありました。
鴨下の作品には蜻蛉や玉虫、蛙、烏賊、蟹、鶏、牡丹、柿、唐辛子などの身近な動植物をモチーフにしたものが多く、そしてそれらはただ写実的に作られる訳ではありません。忠実にスケッチを重ねた上で、おおらかさを出すためにあえて細部を省き、自らのデザインによって生き生きとした作品が作り出されています。
デザインだけでなく、緻密な彫金技術も相まって、雅趣に富む洒落た作品は日本伝統工芸展等でも高く評価され、1999年には重要無形文化財保持者に認定されました。2001年に惜しまれながらも亡くなりましたが、同年勲四等瑞宝章が贈られました。
古美術ますけんでは「鴨下春明」の作品の買取をしております。売却をご検討でしたらフリーダイヤル0120-134-003 又はフォームにてお気軽にお問い合わせ下さい。
|
|
古美術ますけんが選ばれる理由
|
|
|
|
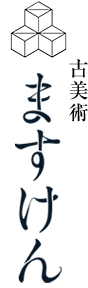
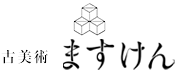
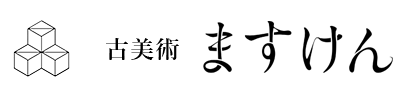
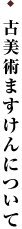
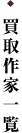
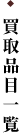
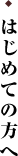
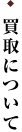
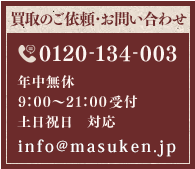
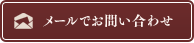
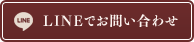






 0120-134-003
0120-134-003 info@masuken.jp
info@masuken.jp ID:@masuken
ID:@masuken
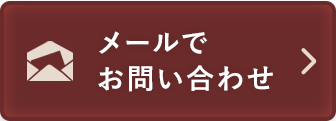
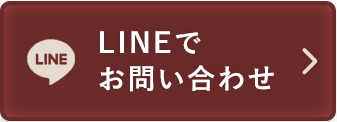
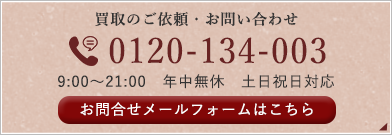
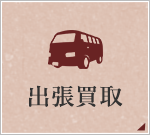
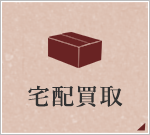

 出張費無料
出張費無料 実績多数
実績多数 安心・信頼
安心・信頼 迅速・丁寧
迅速・丁寧